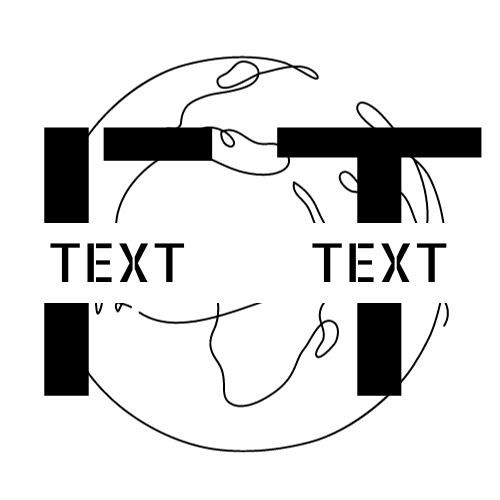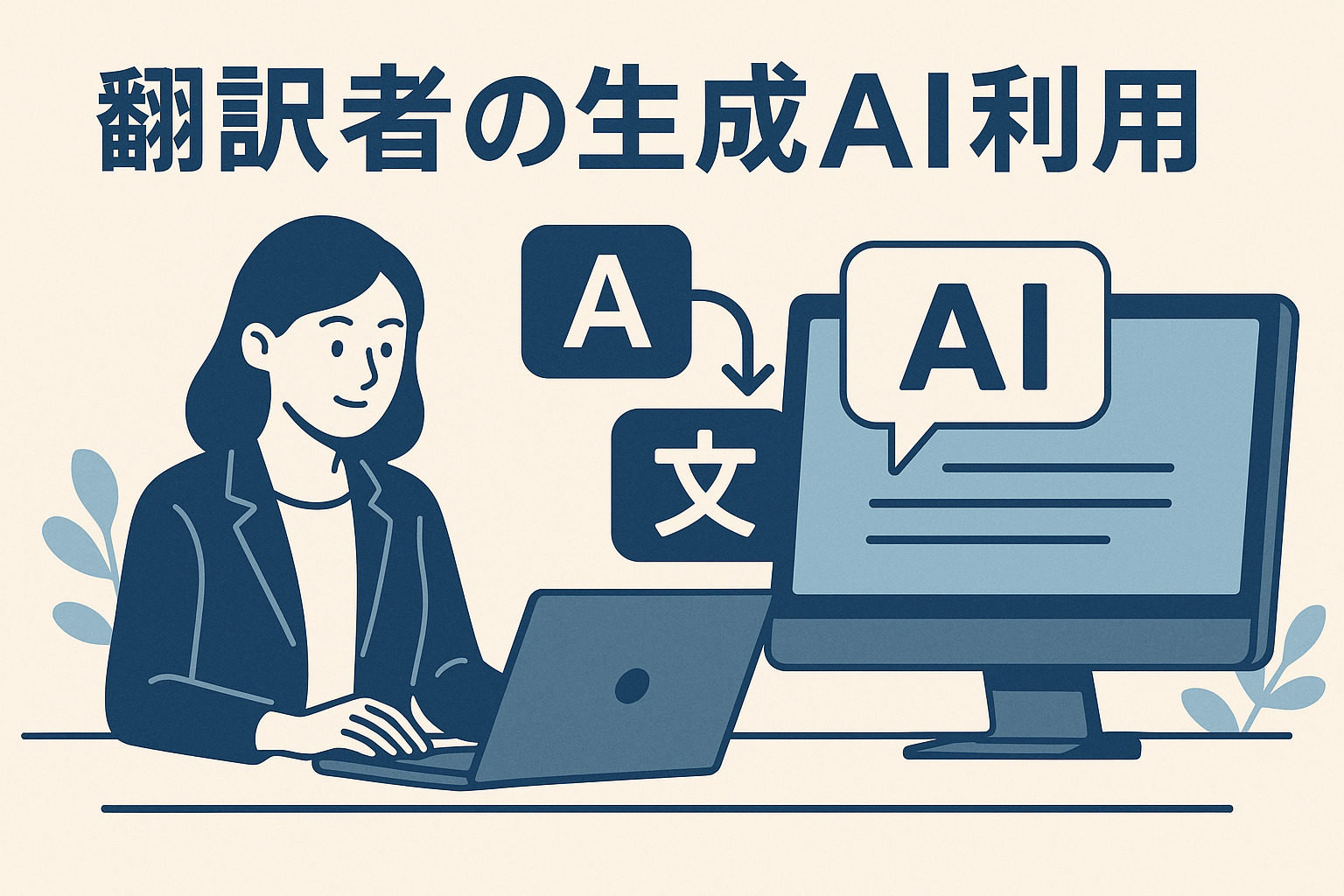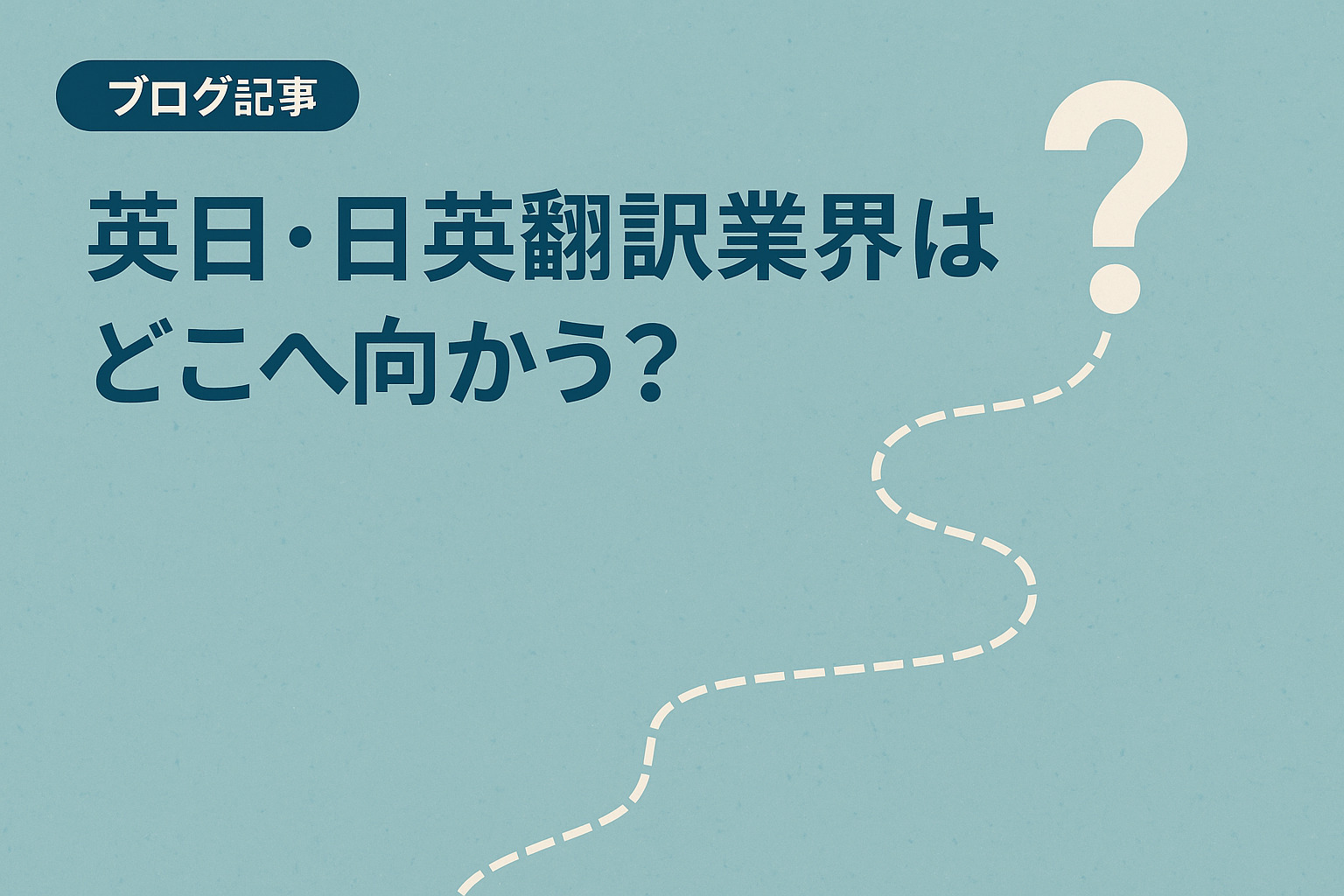最近、ChatGPTやDeepL Writeなどの生成AIを翻訳業務に活かす動きが世界中で一気に広がっています。少し前までは一部の先進的な翻訳者が試験的に取り入れているイメージが強かったかもしれませんが、今やさまざまな調査データが「かなり多くの翻訳者がすでにAIを導入し始めている」と伝えています。
この記事では、最新の調査結果をもとに、翻訳者の生成AI利用率と具体的な活用方法をわかりやすくまとめました。
1. 翻訳者の生成AI利用率はどのくらい?
生成AIの利用率を示す調査は複数ありますが、結果にはばらつきがあります。大きく分けて、
- 文芸翻訳者(英国中心):37%が生成AIを何らかの形で使っている(英国・作家協会 SoA アンケート)
- 翻訳会社(世界28か国):65%が生成AIを定常的に活用している(ALC/Slator業界調査)
- フリーランス翻訳者(欧州全体):実際に使っているのは10%程度(欧州言語産業調査 ELIS)
- フリーランス翻訳者(世界):72%が「生成AIによって日々の業務に変化があった」(ProZ翻訳者コミュニティ投票)
という傾向が報告されています。
数字の幅は大きいものの、「少なくとも全体の1~3割は積極利用しており、近年さらに急増している」という認識でほぼ一致。とくにProZのような国際的翻訳コミュニティでは「7割超の翻訳者がAIの影響を感じている」と回答しており、2023年から2024年にかけて急速に普及が進んでいる実態がうかがえます。
一方、ヨーロッパ全体を対象とする調査(ELIS 2024)では「まだ10%程度にとどまる」という結果もあり、地域や業界の違いによってばらつきがある点が興味深いところです。まだ機械翻訳の品質を懐疑的にみている翻訳者がいたり、守秘義務や著作権の観点からAI利用を控えているケースもありそうです。
2. 具体的にはどう使われている?生成AIの活用方法
翻訳者たちは生成AIの「得意なところ」をうまく活かしながら、生産性と品質向上をめざしています。主な活用法をいくつかご紹介します。
(1) 下訳作成(ドラフト翻訳)
一番多いのが、ChatGPTやDeepLといった高度なエンジンに原文を投入し、ドラフト(初期訳)を作らせる使い方です。AIが生成した仮訳を土台に、人間が微調整を加えることで業務効率をアップ。言語ペアや分野によっては思った以上にレベルが高い翻訳案が出てくることもあり、「まずAIに訳させて時間短縮」という流れが増えています。
(2) ポストエディット
AIで作られた翻訳文を人間がチェック・修正する“ポストエディット”も広く行われています。誤訳の修正だけでなく、文体や用語の整合性チェックも重要。翻訳会社や出版社から「AI翻訳をベースに後編集をしてほしい」と依頼される事例も増加中です。
(3) 文体・スタイルのリライト
DeepL WriteやChatGPTに訳文を投げて「フォーマルに」「カジュアルに」といった指示を与えると、スタイルをガラッと変えてくれます。長文を簡潔にまとめたり、口語調にリライトしたりと、文章全体を“読みやすく仕上げる”サポートもしてくれるので、ネイティブ的な言い回しを手軽にチェックできるのが利点です。
(4) 専門用語のリサーチ
専門分野の略語や背景知識をChatGPTなどで調べる翻訳者も増えています。単純に用語の意味を聞くだけでなく、「XXの分野でよく使われる近い概念は何か?」のように文脈を補足して質問すると、候補を複数教えてくれる場合も。辞書には載っていない微妙なニュアンスの情報や同義語を提案してくれるのは助かりますが、最終的な正確性の確認はもちろん必須です。
(5) 新規コンテンツ作成・クリエイティブ用途
翻訳と直接は関係なくても、ターゲット言語でブログ記事やコピーを書く際に、アイデア出しや文章生成をAIでサクッと済ませる翻訳者も増えています。また、字幕や吹替台本の下訳をAIにやらせるケースもあるなど、音声・映像のローカライズ分野でも活用の幅が広がっています。
(6) その他の便利な使い方
- 用語抽出・グロッサリー作成:長文の中から専門用語や固有名詞をAIに拾わせる
- ファクトチェック:翻訳内容に出てくる統計や歴史的事実をAIに質問して概略を調べる
- 品質評価・校正支援:AIに訳文を読ませて誤訳や不自然な表現がないかのヒントをもらう
- SEO対策:ターゲット言語のキーワード候補を提案してもらったり、メタディスクリプションを生成させたり
こうした多岐にわたる活用が進む中で、「AIは便利だけど誤訳や事実誤認もあるから注意が必要」といった声も多いようです。
3. 今後の展望
生成AIを活用する翻訳者は今後さらに増えていくと予想されます。ただし、「AI頼みで品質を落としたくない」という慎重派も少なくありません。実際に欧州の調査ではAI利用率が1割程度とまだ低かったり、守秘義務やデータ流出のリスクから導入に慎重な意見も存在するなど、“積極派”と“様子見派”の温度差は依然大きいようです。
それでも、急速に進化する生成AIの性能や周辺ツールの整備状況を考えると、翻訳者の間で「AIをまったく使わない」という選択肢はどんどん難しくなるかもしれません。大切なのは、AIを正しく理解し、人間の専門性とうまく掛け合わせること。誤訳や文脈のズレを最終的に判断できるのは人間であり、そこにこそプロ翻訳者の価値があるからです。
翻訳業界でも、AI利用に関するガイドラインや研修の整備が進み始めています。今は過渡期ともいえますが、「AI時代における翻訳の質をどう担保するか」「翻訳者のスキルをどう活かすか」といったテーマは、これからますます注目されることになるでしょう。
参考資料
- Society of Authors (2024年調査結果)
- ALC/Slator Industry Survey (2024)
- European Language Industry Survey (ELIS 2024)
- ProZ Quick Poll (2025)
- Rivas & Moorkens (2024)「A year of ChatGPT: translators’ attitudes and degree of adoption」
- American Translators Association (ATA) ブログ (2023)
- The Guardian (2024年4月16日)
いかがでしたか?
一口に生成AIといっても、翻訳の下訳からクリエイティブな新規文章作成まで、本当にいろんな形で使われています。これからも新しいAIツールや事例がどんどん生まれるはず。翻訳者にとっては「うまく使いこなせれば大きな武器になる」という側面がある一方で、情報の正確性や守秘義務に配慮して慎重に使う必要もあります。
皆さんの現場では、どのように生成AIを活用していますか? これからも最新動向を追いつつ、賢くAIと共存していきたいですね。