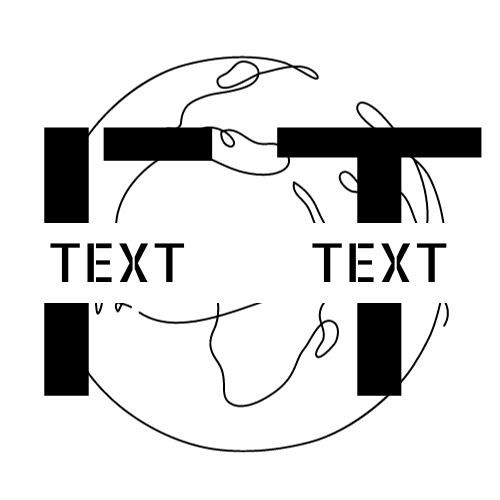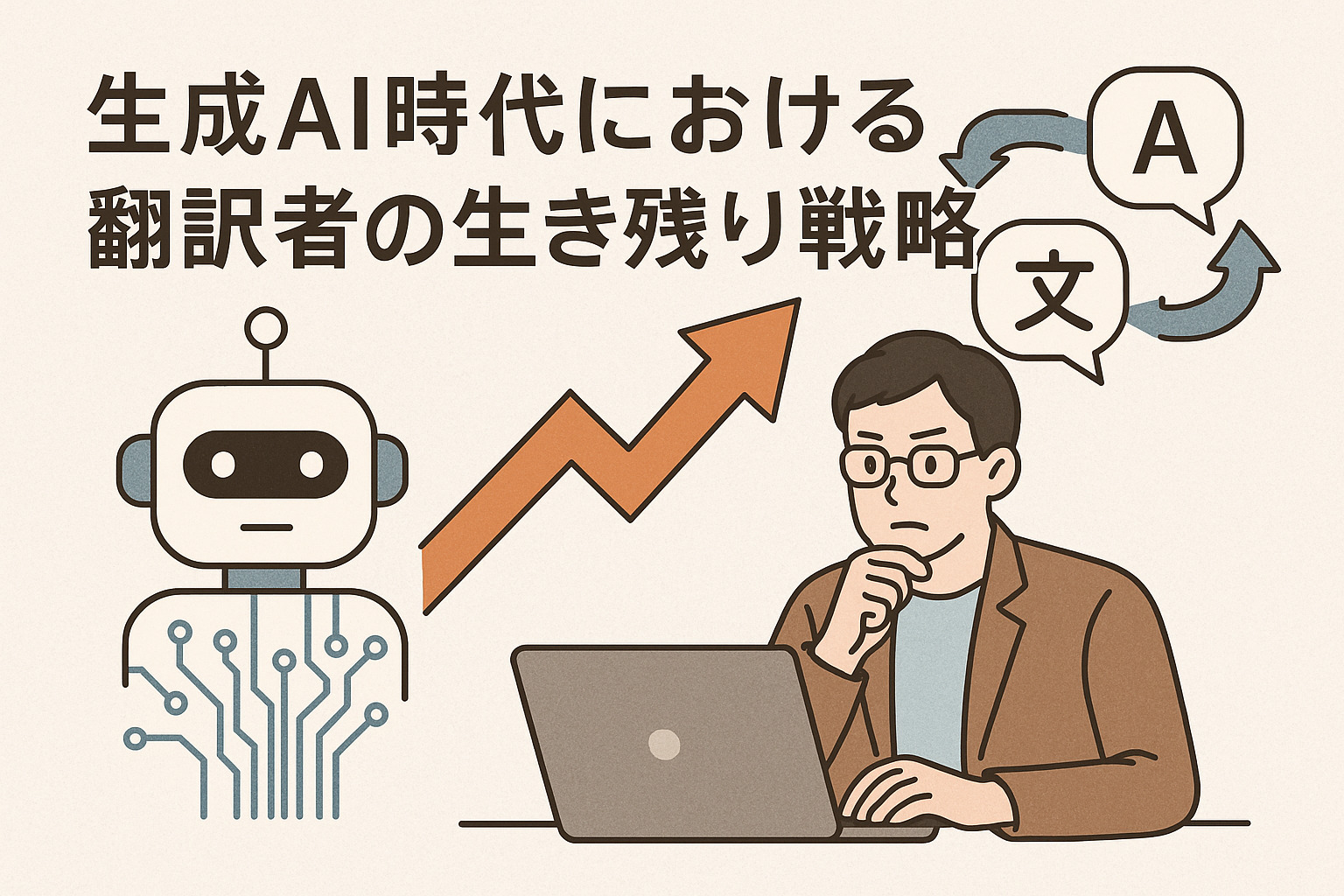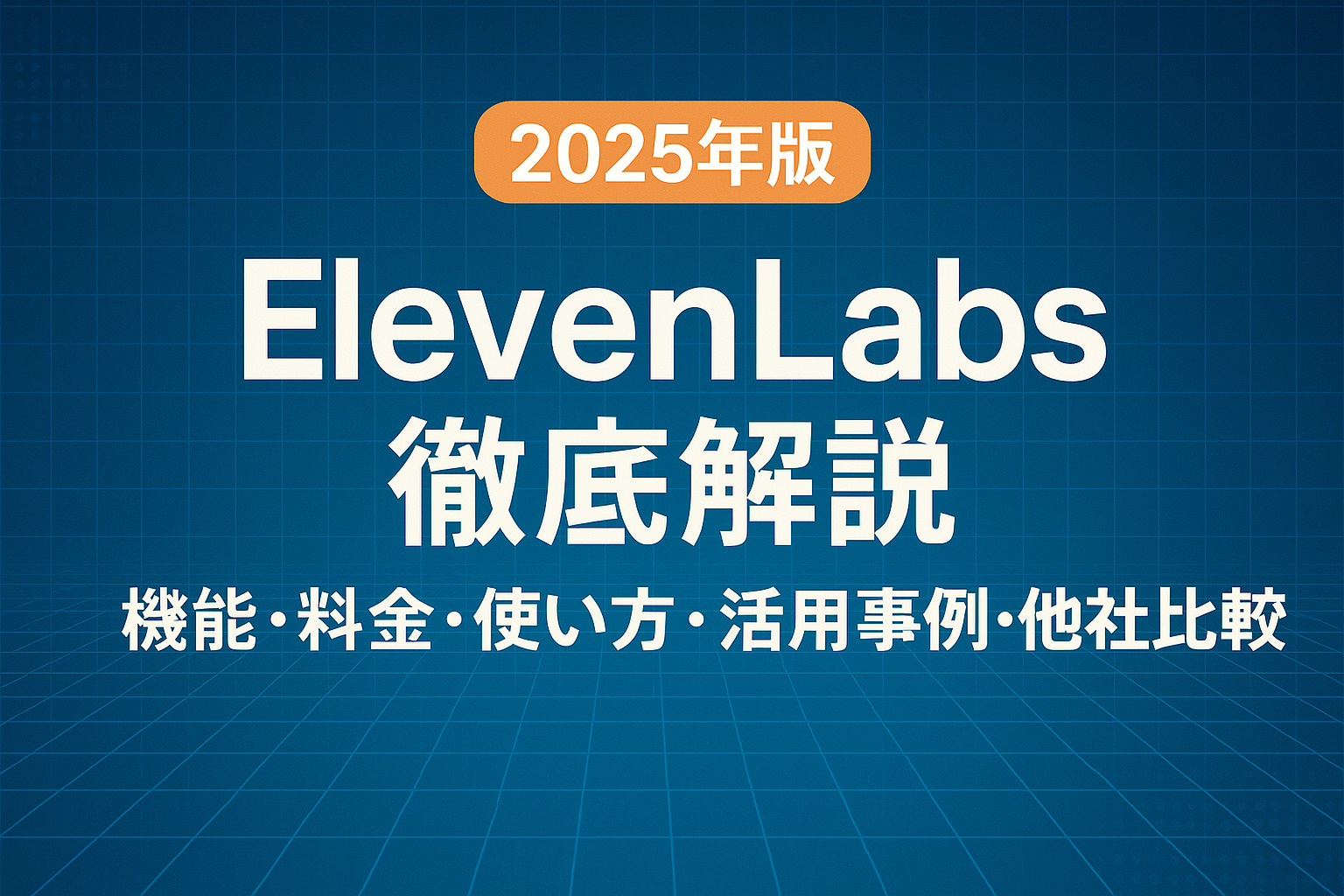日本国内では、英語力を証明するためのさまざまな資格試験が実施されています。成人が受験できるあらゆるレベル(初級~上級)に対応した試験があり、ビジネス用途や学術用途など目的も様々です。本調査では、主要な英語試験について試験名称、概要(目的・形式)、難易度やレベル範囲(CEFRやスコア等)、実施頻度・日程、利用目的、おすすめの対象者、メリット・デメリットといった観点から比較します。まず主要な試験の比較表を示し、その後に各試験の特徴や活用状況、利点・欠点を詳述します。
主な英語試験の比較表
以下の表に、日本で広く受験されている英語資格試験の基本情報をまとめます(初級~上級まで対象)。各試験の出題形式や難易度の目安、実施頻度や主な利用目的を比較しています。
| 試験名 | 概要・特徴(目的・出題形式など) | 難易度・レベル範囲 | 実施頻度・試験日程 | 主な利用目的 |
|---|---|---|---|---|
| TOEIC(L&R中心) | ビジネスや日常場面での英語コミュニケーション能力を測定。リスニング&リーディング中心の選択式試験(990点満点)。※スピーキング&ライティング試験も別途あり | 初級~上級(スコア10~990)。CEFRではA1~C1程度まで測定可能 | 年約10回の公開テストを全国で実施(L&R)。S&Wは月2回程度開催。通年受験可。 | 就職・昇進(企業での評価基準)、大学の単位認定や卒業要件。国内で最も受験者が多い試験 |
| 英検(実用英語技能検定) | 文科省後援の4技能試験。日常会話から社会性の高い話題まで幅広く出題。級別(1級~5級)に筆記+リスニング、合格者は二次で面接。コンピュータ形式の「英検S-CBT」も導入。 | 入門~最上級(5級~1級)。1級はCEFR C1相当、準1級はB2程度、2級はB1程度。級ごとに合否判定。 | 年3回(1~3次)実施。一次(筆記)と二次(面接)は別日程(S-CBTでは1日完結可能)。 | 中学・高校・大学受験(入試優遇・単位認定)、教員採用、自己研鑽。国内認知度が高く約1700校で活用。 |
| TOEFL iBT | 英語を母語としない人向け学術英語試験。大学講義や論文に対応する読解・講義聴解、英文ライティング、スピーキングを測定。インターネット形式で4技能を総合評価(120点満点)。 | 中級~特上級(CEFR B1~C1/C2)。大学入学に必要なスコアは80~100点台(B2~C1相当)。高得点ではネイティブ並みの高度な語学力。 | 年間40~45回程度、全国の指定会場で実施。日時は通年で複数、予約制。 | 海外大学・大学院留学、交換留学の出願要件(米国含む150か国以上・1万超の機関がスコア採用)。 |
| IELTS(Academic/General) | 英国文化圏主体の4技能試験。Academic版は大学教育に必要な英語力評価、General版は移住や就労向け。リスニング・リーディング・ライティング(筆記/PC選択可)+対面スピーキング。バンドスコア0~9で評価。 | 中級~特上級(CEFR B1~C2)。例えば総合6.0でB2程度。大学学部留学には6.0~7.0以上が目安(B2~C1)。 | 年間約40回と実施回数が多く、月に数回実施。全国主要都市で開催(紙またはコンピュータ試験)。 | 海外留学(特に英国・豪州・欧州)、移住申請(永住・ビザ要件)、国内大学入試の外部試験にも利用。一部英連邦系企業での採用基準。 |
| ケンブリッジ英検(Cambridge English) | ケンブリッジ大学英語検定機構の資格試験群。レベル別にCPE(C2),CAE(C1),FCE(B2),PET(B1),KET(A2) 等があり、実生活での英語運用力を評価。読写聞話の4技能をバランスよく測定。 | 初級~最上級(CEFR A2~C2まで各試験で対応)。CPE合格はC2(熟達したレベル)、FCE合格でB2(独立したユーザー)等。資格は合否判定で一度取得すれば有効期限なし。 | 公開試験は年3~4回程度(レベル・会場により異なる)。全国の試験センターで実施。日程はレベルごとに設定(例:FCE年4回等)。 | 欧州や英連邦圏での就学・就職(世界20,000以上の機関で認証)。英語教養資格として評価され、国内では帰国子女や高度専門職での活用例も。 |
※上記の受験料や日程は変更される場合があります。TOEIC・英検など日本発の試験は国内での認知度が非常に高く、TOEFL・IELTS・Cambridgeは海外でも通用する国際的な英語資格です。
各試験の概要と特徴
上記の比較表で概観した主要試験について、それぞれもう少し詳しくおすすめの受験者像やメリット・デメリットを含め解説します。
TOEIC(トーイック)
概要・目的:TOEICは主にビジネスにおける実践的な英語コミュニケーション能力を測定する試験です。1979年に日本で初めて実施されて以来40年以上の歴史があり、年間受験者数は約210万人(2022年度、TOEIC Program全体)にも上ります。試験はListening & Reading(L&R)テストが中心で、日常業務や生活場面を想定した英文の聞き取りと読解問題で構成されます(マークシート方式、約2時間)。スピーキングとライティング能力を測定する「TOEIC Speaking & Writing (S&W)」もありますが、L&Rと別日に実施されます。スコアは10~990点の範囲で5点刻みで評価され、英語運用力の指標となります。
難易度・レベル範囲:初心者から上級者まで幅広いレベルに対応しています。例えばTOEICスコアとCEFRレベルの関係では、TOEICで約550点がB1(中級)相当、785点以上でB2(上級前半)相当、945点以上でC1(上級)相当とされています。TOEICでは満点990点でもCEFRの最高位C2には達しないため、ネイティブ級の熟達度評価には向きません。とはいえ、スコア800点台後半~900台で高度な英語力を示す指標となります。
実施頻度:公開テスト(L&R)は年約10回と実施頻度が高く、全国47都道府県で受験可能です。試験日は月1回程度(地域によっては隔月)で設定され、平日開催も一部あります。S&Wテストは主要都市で月2回程度実施されます。何度でも受験でき、有効期限も公式には定められていないため(※スコア証明書の再発行は試験日から2年以内)、継続的に挑戦してスコアアップを図る人も多い試験です。
利用目的:就職や昇進の場面で圧倒的な認知度があります。日本企業の多くがTOEICスコアを社員採用・評価基準に取り入れており、特に600点台後半~730点以上を応募条件とするケースも見られます。また大学では、入学時のクラス分けや在学中の単位認定・卒業要件としてTOEICスコア提出を求めるところもあります。国内で英語力を証明する指標として最も広く使われており、「とりあえずTOEIC○○点」といった目標設定が一般的です。
おすすめの受験者:日本国内で就職・転職を有利に進めたい大学生・社会人に特におすすめです。業種を問わず企業知名度が高いため、「英語ができる」とアピールする際の分かりやすい指標になります。また、英語初中級者がビジネス英語に触れるきっかけとして受験するのも良いでしょう。リスニングとリーディング能力に特化しているため、まずは読む・聞く力を重点的に伸ばしたい人にも適しています。
メリット:
- 国内での知名度抜群: 企業や教育機関で評価基準として広く採用されており、就職・昇進で活用しやすい。結果を履歴書に書きやすい。
- 受験機会が多い: テスト実施頻度が高く、短期間で再挑戦しやすい。スコアの伸びを定期的にチェックする使い方も可能です。
- 対策が取り組みやすい: 問題形式が毎回ほぼ一定で、リスニング&リーディングのみのため範囲が絞りやすい。教材や対策講座も豊富です。
デメリット:
- 測定技能が限定的: 通常のTOEIC L&Rでは話す・書く力を測定しないため、総合的な英語運用力の証明には不十分です(スピーキングやライティング力は別試験で補完が必要)。
- 国際的認知度の低さ: 日本や韓国など一部の国以外ではTOEICの知名度は高くなく、海外留学や移住用途には適しません 。海外大学の出願要件にTOEICが使われることは稀です。
- 高得点でもC2証明不可: TOEICはCEFRでC1レベルまでしか対応しておらず、ネイティブ並みの最上級者でも測定上限がある。語彙・内容もビジネス日常寄りで、学術的な英語力は反映しにくいです。
英検(実用英語技能検定)
概要・目的:英検は日本の文部科学省後援の英語検定試験で、1963年創設という長い歴史を持ちます。読む・聞く・書く・話すの4技能を段階別に評価することを目的としており、日常的な話題から社会性のある題材まで幅広い内容が出題されます。受験級は5級(入門レベル)から1級(最難関)まで7段階あり、それぞれの級ごとに筆記(リーディング・ライティング)+リスニングの一次試験と、合格者のみ**面接形式の二次試験(スピーキング)**があります。1級では高度な語彙力(1万語以上習得が目安)や全技能のバランスが要求され、合格は難関資格として知られます。
難易度・レベル範囲:初級者向けの5級から、英語専門職でもアピール材料となる1級まで難易度の幅が非常に広い試験です。英検各級は独自のCSEスコアで評価され、これがCEFRレベルに対応しています(英検CSEスコアによる公式対応)。概ね1級はCEFR C1相当、準1級はB2、2級はB1、準2級はA2-B1程度、3級はA2、4級はA1+、5級はA1程度とされています。したがって英検1級合格者は国際基準でも上級(C1)レベルとみなせます。また級ごとの合否判定制度のため、一定基準に達すれば合格証が取得できます。なお有効期限はなく、取得した級は生涯有効な資格として扱われます。
実施頻度:本会場での試験は年3回(例年6月・10月・翌年1~2月頃)定期実施されます。一次試験(筆記・リスニング)は全国47都道府県で開催され、合格者対象の二次試験(面接)はその約1か月後に別日程で行われます。近年は英検S-CBTと称するコンピュータ受検形式も導入され、従来は別日だったスピーキング含め1日で4技能を完結する受験も可能になりました。英検S-CBTは年数回~月1回程度、会場限定で実施されています。また準会場制度により、学校など団体経由での受験も盛んです。
利用目的:学校教育や入試との結びつきが強い試験です。英検の各級合格やスコアは、中学・高校・大学の入学試験や単位認定で幅広く利用されています。特に準2級~2級は高校卒業程度、準1級以上は大学中~上級程度の英語力証明として、多くの教育機関で優遇措置があります。例えば英検〇級取得で高校受験の内申加点や、大学推薦入試での出願資格になるケースもあります。また英語教師・講師を目指す人や、語学力を証明したい社会人が自己研鑽として受験することもあります。1級合格者には、通訳案内士試験の英語科目免除などの特典もあります。
おすすめの受験者:英語初学者から中級者まで段階的に挑戦したい人に向いています。5級・4級は中学初級程度、3級は中学卒業程度と学習進度に沿ったレベル設定で、ステップアップの目標にしやすいです。また国内志向の学生(日本の高校・大学入試で有利にしたい人)にとって必須級とも言える試験です。一方で1級は非常に難易度が高く、英語専門職を目指す上級者におすすめです。英検1級合格は希少価値が高く、英語講師や翻訳・通訳業で能力の裏付けとして評価されます。
メリット:
- レベル設定が細かく達成感に繋がる: 7つの級が用意されており、自分の現在の実力に合った級から段階的に力試しができます。合格すれば公式の認定証が得られ、モチベーションアップに繋がります。
- 学校・受験で強い効力: 国内約1700の中学・高校・大学で入試や単位認定に利用されるなど教育現場での活用が広範です。特定級の取得で受験を有利に進められるケースも多いです。
- 4技能をバランスよく習得できる: 読む・書く・聞く・話す全てを評価するため、英語力を総合的に伸ばす学習につながります。S-CBTなら1日で4技能受験でき、効率的です。
デメリット:
- 海外での認知度は低い: 英検は日本独自の試験であり、海外の大学や企業では基本的に英語力証明として通用しません。留学や移住にはTOEFL/IELTSなど別試験が必要です。
- 試験機会が限られる: 通常の公開試験は年3回のみで、結果待ち期間も含め次の挑戦まで間隔が空きます。合否制のため不合格だと成果が残らず、学習継続の上でモチベーション管理が必要です。
- 高級ほど語彙・内容が難解: 準1級~1級では出題語彙が非常に難しく専門的で、実用性よりも試験対策的な勉強が必要になる傾向があります。難関級へのハードルが高い点は上級者でも挫折しやすい部分です。
TOEFL iBT(トーフル・アイビーティー)
概要・目的:TOEFL iBTは、英語圏の大学教育で必要となる英語力を測定することを目的とした試験です。米国の教育試験サービス機関ETSが運営し、インターネットを介して出題・解答する4技能試験となっています。内容は大学の講義や教科書に基づくアカデミックな文章の読解(Reading)・講義や会話の聴取(Listening)・意見や要約の英作文(Writing)・学術的トピックについてのスピーキングで構成されます。各セクション30点満点×4で合計0~120点のスコアが算出されます。試験時間は約3時間(以前は約4時間でしたが2023年以降短縮)で、受験者同士が同室でPCに向かいヘッドセットで受験する形式です。
難易度・レベル範囲:TOEFLは中上級~最上級者向けと言われ、他の試験と比べても難易度が高めです。特にリスニング・リーディングの題材が大学レベルの学術内容(生物学、歴史学など)で専門用語も多く含まれるため、日常英語に慣れただけでは高得点は難しいでしょう。ただしスコアレンジは幅広く、新興の英語話者でも頑張ればスコア30~40点台からスタートできます。CEFR対応では、TOEFL iBTスコア42点程度でB1(中級)、72点程度でB2(上級前半)、94点以上でC1相当とされます。名門大学院などは100点超(C1上位~C2近く)を要求することもあり、最上位層の判別にも使える試験です。
実施頻度:世界中で実施されており、日本国内でも年間40~45回程度の試験日が用意されています。ほぼ毎週末どこかで実施されているイメージで、地域によっては月に数回選択肢があります。受験地は北海道から沖縄まで28都道府県で展開され、オンラインで事前予約して希望日・会場を選びます。また自宅で受験できるTOEFL iBT Home Editionも導入されており、自宅のPCから監督下で受験することも可能です(要設備要件)。結果は試験日から約6日後にオンライン発表されます。スコアの有効期限は2年間です。
利用目的:TOEFLは主に海外の大学・大学院への出願目的で利用されます。米国・カナダをはじめ世界150か国、10,000以上の教育機関で公式な英語力証明として認められており、特にアメリカではTOEFLスコア提出が一般的です。日本国内でも英語大学院コースや国際系学部の入試でTOEFLスコア提出を課す場合があります。また企業によってはグローバル人材採用や社内公募でTOEFL◯点以上を目安とすることもありますが、頻度としては少数です。基本的には**「留学用試験」**と認識されており、英語圏留学希望者には避けて通れない存在です。
おすすめの受験者:海外留学を目指す学生・社会人には必須に近い試験です。特に北米留学志望ならIELTSよりTOEFLを指定されることが多いため、早めに対策を始めるのがよいでしょう。またアカデミックな英語力を客観評価したい人にも適しています。英語で専門書を読んだり講義を受けたりする力を測れるため、純粋な英語力試しとしても非常に歯ごたえがあります。逆に、ビジネス英語や日常会話力を図りたい人、あるいは留学予定がない人にはオーバースペックぎみなのでおすすめしません。
メリット:
- 海外大学での圧倒的受容度: TOEFLは世界中の大学で公式に認められており、米・英・豪など主要国の大学入学要件をこれ一つでカバーできます。留学用途では最も汎用性の高い英語試験です。
- 4技能の総合力評価: リーディングからスピーキングまでバランスよく測定され、アカデミックな総合英語力が数字で示されます。各セクション毎の得点も出るため、自分の弱点把握にも役立ちます。
- 試験日程が豊富: 年間を通して実施回数が多く、自分の留学準備スケジュールに合わせて受験計画を立てやすいです。急にスコアが必要になった場合も比較的すぐ受験できます。
デメリット:
- 受験料が高額: 1回の受験に約US$195(約3万円強)かかり、繰り返し受験する経済的負担が大きいです。留学検定料として他の出願費用と併せ重荷になりがちです。
- 試験が難しく長丁場: 問題内容は高度で専門的、分量も多いため非ネイティブには難関です。また試験時間も3時間超と集中力の維持が大変で、精神的・体力的負担が大きいと言われます。
- 国内での認知度限定: 留学以外の場面ではTOEFLスコアを活かす機会は限定的です。日本企業ではTOEFLよりTOEICを評価する所が多く、せっかく高スコアでも活用できない場合があります。
IELTS(アイエルツ)
概要・目的:IELTSはイギリス・オーストラリアなどが中心となって開発した、TOEFLと並ぶ国際的な英語力評価試験です。AcademicモジュールとGeneral Trainingモジュールの2種類があり、Academicは大学・大学院進学希望者向けに高等教育レベルの英語力を測る内容、Generalは主に移住申請や就労ビザ取得など生活・職場での英語力証明向けの内容となっています。試験構成はいずれもListening(約30分)、Reading(60分)、Writing(60分)、Speaking(10~15分)の4技能です。リスニングとリーディングは選択式、ライティングは与えられた課題について記述式解答、スピーキングは試験官との対面インタビュー形式で行われます。特徴的なのはスピーキングが対人である点で、これは録音応答のTOEFLと対照的です。評価は各技能を0~9のバンドで採点し、その平均を**総合バンドスコア(0.5刻み)**として提示します。
難易度・レベル範囲:IELTSも中級者から上級者向けの試験ですが、バンドスコア制のため受験者のどのレベルでも結果が数値化されます。例えばバンド4.0でCEFR B1弱(英検2級相当)、6.0でB2(準1級相当)、7.0でC1(1級相当)といった換算になります。最高の9.0は文字通りネイティブ同等以上のC2レベルです。TOEFLに比べると難易度の体感は若干低めとの指摘もあり、特に日本人にはIELTSの方がスコアが取りやすいという意見もあります。これは試験構成上、一度に取り組む設問が比較的短く区切られ明確な点や、TOEFLより馴染みのある生活寄り話題も含まれるためです。ただし高得点を取るにはもちろん高度な英語運用力が必要です。
実施頻度:IELTSは日本国内では月に3~4回程度実施されており、年間約40回と非常に試験機会が多いです。試験主催はブリティッシュ・カウンシルおよび公益財団法人日本英語検定協会(英検)が共同で行っており、東京・大阪など主要都市はもちろん地方含め全国16都市以上で開催されています。試験日は主に土曜日または木曜日が多く、スピーキングのみ別日程で前後に設定されることもあります。近年は一部会場でコンピューター受験(CDI: Computer-Delivered IELTS)も導入され、こちらは試験結果が通常より早く(5~7日程度)出るメリットがあります。IELTSのスコア有効期限も2年間です。
利用目的:海外留学・研修や移住(ビザ取得)の用途でTOEFLと並ぶ代表的な試験です。特にイギリス、オーストラリア、ニュージーランド、カナダなど英連邦諸国の高等教育機関ではIELTS提出が標準です。また英国・カナダ・豪州などの移民局が永住権やビザ申請者にIELTS(General)の一定スコア提出を課す場合があります。日本国内でも、大学の海外留学プログラム応募や帰国子女入試などでIELTSスコアが利用されます。近年はアメリカの大学でもIELTS受入が拡大し、米国約3,000校以上がTOEFLの代替として認めています。ビジネスではTOEICほどではないものの、国際企業で昇進要件にIELTSを使う例も一部あります。
おすすめの受験者:イギリス・欧州・オセアニア方面への留学や移住を考えている人には最適です。各国のビザ要件等も調べ、自分に必要なIELTS種類(AcademicかGeneralか)を確認しておきましょう。またスピーキング試験を対面で受けたい人にも向いています。人と会話する形式の方が力を発揮できる人、あるいはスピーキング力そのものを鍛えたい人にはTOEFLよりIELTSがおすすめです。一方、日常的な英語コミュニケーション力の証明にもなるため、TOEFLほど学術寄りでなく総合的な英語力を測りたい中上級者にも適しています。
メリット:
- 幅広い国・目的に対応: TOEFLがカバーしきれないイギリス圏や移住用ニーズまでカバーしており、受験者の目的によってAcademic/Generalを選択可能なのは利点です。オールマイティな英語試験と評されることもあります。
- 試験機会と受験地が豊富: 国内実施回数が多く、また試験地も全国にわたり受けやすいです。コンピューター実施も含め日程選択の柔軟性があります。結果も比較的早く出るためスケジュール管理しやすいです。
- スピーキングが対話形式: 面接官との会話なので、回答が機械的でなく双方向コミュニケーション力を示せます。表情やイントネーションも含め評価されるため、会話力に自信がある人には有利でしょう。
デメリット:
- 受験料が高い: 受験料は約25,000~27,000円前後と高額で、複数回受験すると経済的負担になります。国際的な試験ゆえやむを得ませんが、学生には痛手です。
- ライティング採点が辛め: IELTSのライティングセクションは採点が厳しい傾向があると言われ、論理構成や文法精度への要求水準が高いです。独学対策では高得点が伸び悩むケースもあります。
- 日本国内での企業認知は限定: TOEICと比べ国内一般企業でIELTSスコアを評価できる人事担当者はまだ少数です。したがって国内就職だけが目的ならコストに見合わない可能性があります。
ケンブリッジ英検(Cambridge English Qualifications)
概要・目的:ケンブリッジ英検は、イギリスのケンブリッジ大学英語検定機構が提供する世界的に権威ある英語資格試験です。特定の試験名ではなく、レベル別に複数の試験が体系化されています。代表的なのは大人・一般向けの以下のメインスート試験です:
- C2 Proficiency (CPE) – CEFRレベルC2対応(最上級)
- C1 Advanced (CAE) – CEFRレベルC1対応(上級)
- B2 First (FCE) – CEFRレベルB2対応(中上級)
- B1 Preliminary (PET) – CEFRレベルB1対応(中級)
- A2 Key (KET) – CEFRレベルA2対応(初級)
これらはいずれもリーディング・リスニング・ライティング・スピーキングの4技能を包括的にテストし、合否またはスコアで結果が示されます。出題内容は日常生活や社会・職場など実用的な英語力を問うものが多く、例えばメール文書作成、プレゼンテキスト読解、対話など実践的です。またビジネス分野に特化したBusiness English Certificate (BEC)も別途あり、中級~上級(B1~C1)向けにビジネス英語力を証明する試験として提供されています。
難易度・レベル範囲:試験ごとに対応するCEFRレベルが決まっており、受験者は自分の到達レベルに合った試験を選んで受験します。例えばFCEなら主にB2レベル判定用で、合格(合格スコア取得)すれば「レベルB2達成」と認定されます。高得点だと上位レベル(例えばFCEで優秀な成績だとC1相当認定)も得られる仕組みです。一方で不合格でも下位レベル(例えばB1)の証明書が発行される場合があります。CPEは世界最高峰レベルの試験で、合格はネイティブ並みの高度な英語運用力と見なされます。各試験とも合否制ですが、細かなスコアも付与され、自分の技能ごとの評価も得られます。資格の有効期限は無制限で、一度合格すればその資格は一生有効なのも特徴です。
実施頻度:ケンブリッジ英検は日本では他試験ほど頻繁ではないものの、各レベル試験が年に数回定期実施されています。たとえばB2 First (FCE) や C1 Advanced (CAE) は年3~4回、C2 Proficiency (CPE)は年1~2回程度の機会があります。試験日は全世界共通日程で、試験センターごとに実施有無が決まります。日本では一般財団法人日本ケンブリッジ英語検定機構や河合塾などが公開テストを運営しており、公式カレンダーで年間日程が公開されています。試験形式は筆記試験(PBT)が基本ですが、近年一部レベルではコンピュータ形式も選択可能です。受験地は東京・大阪など都市圏が中心で、地方では試験センターが限られます。
利用目的:ケンブリッジ英検は世界130カ国以上で年間約250万人が受験しており、英語資格の国際標準の一つとされています。特にヨーロッパ諸国では就職・昇進や大学入学における英語証明として定着しており、20,000以上の教育機関・企業・政府機関で認証されています。日本国内ではまだ知名度は高くないものの、英語教員採用や一部大学の英語研修派遣選考などで評価対象とする例もあります。また一生ものの資格として、上級者が腕試しに取得を目指すケースも見られます。英検1級やTOEFL高得点と並び、「本当に英語ができる人」の指標として業界関係者には知られています。
おすすめの受験者:国際的に通用する資格が欲しい上級学習者に向いています。特に欧州やグローバル展開企業で働きたい人は、TOEICよりもケンブリッジ系資格の方が評価される場合があります。また英語力を客観的に証明したい教師・翻訳者などにも最適です。中級レベルのFCEやPETは、TOEFL/IELTSほど難解ではなく日常的な英語力を見るので、日常・旅行英語を磨きたい社会人にも良い挑戦となります。ただ、受験料がやや高めで試験機会も限られるため、本気で資格取得を目指す熱意のある人向けと言えます。
メリット:
- 取得すれば永久有効: 合格証明に有効期限がなく、一度取得すればその英語力をずっと証明できます。履歴書等にも常に書ける資格として価値があります(TOEFL/IELTSは2年で期限切れ)。
- 実践的でバランス良い試験: すべての試験で4技能を均等に測定し、試験内容も実用的なコミュニケーション重視です。真の英語運用能力を鍛える学習過程となり、「使える英語力」が身につくと言われます。
- 国際的な権威と信頼性: ケンブリッジ大学の試験というブランドがあり、グローバルで信用度が高いです。英語圏出身者でも履歴書に書く価値がある資格として認知されています。
デメリット:
- 受験環境が限られる: 日本では受験できる都市・日程が少なく、地方在住者にはハードルがあります。試験情報も英検やTOEICほど簡単に得られず、受験手続も英語サイト経由だったりと手間がかかります。
- 試験対策情報の不足: 世界的試験のため日本語の参考書や対策講座が少なめです。独学で公式過去問などを使う必要があり、ハードルを感じる人もいます。
- 難易度調整が必要: 自分のレベルより高い試験を受けても不合格だと資格が得られず無駄になりかねません。逆に易しすぎる試験では能力証明にならないため、自分に合った級選びが重要です。
その他の英語資格試験
上記以外にも、日本国内で成人が受験可能な英語試験はいくつか存在します。それぞれ専門的な目的や特徴がありますので、主なものを簡単に紹介します。
- GTEC(ジーテック): ベネッセコーポレーションが提供する4技能型テスト。学校教材として開発され、高校・大学での英語力測定や入試利用が増えています。コンピュータ受験でListening/Reading/Writing/Speakingを1日で受験可能。スコアは合否ではなくスコア制(Advancedで0~800点)。CEFRにも対応し、学生の英語力を手軽に把握できるのが利点です。メリット: 年間複数回実施され、学校単位で受けやすい。国内大学の入試でも120以上の大学で活用実績。デメリット: 国際的な認知度は低く、海外留学用途には使えません。社会人には馴染みが薄く、主に学生向けの試験です。
- TEAP(ティープ): 上智大学と英検協会が開発したTest of English for Academic Purposes。日本人高校生向けに、大学教育で必要な英語力を測定する試験です。4技能を測定し、試験内容も日本の大学入試を意識したアカデミック寄りになっています。メリット: 日本の大学入試用に最適化されており、国内約120大学でTEAPスコアを外部試験として利用可能。デメリット: 対象が限られ、社会人や海外大学には通用しません。実施も年3回程度と限られます。
- 国連英検(国際連合公用語英語検定): 日本国際連合協会主催の試験で、「国際協力」「異文化理解」に関する知識と英語運用力を測るユニークな検定です。級はE級(入門)から特A級(最難関)まであり、B級以上になると国連や国際問題に関する英文読解・論述・面接が課されます。メリット: 国連や国際機関への関心を示すアピールとなり、上位級合格者は難関資格として評価されます。デメリット: 出題が特殊で対策が必要なこと、合否判定で上位級は非常に難しく受験者も少ないこと、またこの資格自体を直接認定要件にする就職先は限られることが挙げられます。
- 日商ビジネス英語検定: 日本商工会議所が実施するビジネス実務に特化した英語検定です。3級~1級まであり、貿易書類・ビジネス文書の読解やEメール作文など、実際の商取引で使われる英語力を問います。メリット: 勉強を通じて実務英語(貿易・会計用語など)が身につく実利があります。貿易事務や海外営業担当者におすすめ。デメリット: 知名度が限定的で、取得しても評価する企業は商社など一部です。TOEICなどに比べ一般的ではありません。
- GCAS (Global Communication Ability Scale): ビジネスシーンでの英語スピーキング能力に特化した試験です。面接官と1対1で約15分間、経営・マーケティング・人事など様々な業務シチュエーションを想定した対話を行い、CEFRレベルで評価が出ます。メリット: 実際のコミュニケーション力を測れるため、スピーキング強化の目標として有用。企業の研修担当者や管理職層から支持されており、社内評価に組み込む例もあります。デメリット: スピーキング単独の評価なので総合力証明とはならないこと、実施団体が限られ受験機会が少ないこと、知名度もまだ高くない点です。
- Duolingo English Test (デュオリンゴ英語テスト): 最近注目度が急上昇しているオンライン完結型の英語試験です。インターネット環境があれば24時間いつでも自宅受験でき、約1時間で全セクションが終了します 。AIが出題を受験者レベルに応じて調整する適応型テストで、リスニング・リーディング・スピーキング・ライティングを網羅し160点満点のスコアが出ます。メリット: 受験料はわずか$49(約6,600円)と他試験より格安。受験後48時間以内に結果が判明し、3,500以上の教育機関(イェール大学やコロンビア大学など含む)が入学資格として採用しています。日程・場所の制約なく受験できる手軽さは突出しています。デメリット: 新しい試験のため一部の大学・機関では未対応の場合があります。また完全オンラインゆえ不正防止の厳格なルール(身分証提示やカメラ監視など)があり、慣れないと戸惑うかもしれません。日本国内企業での認知度もまだ低いため、現時点では主に海外留学志望者向けと言えます。
以上、主要な英語資格試験の特徴と比較をまとめました。英語試験ごとに目的や形式が異なるため、自分の英語力を活かしたい場面や現在のレベルに合わせて最適な試験を選ぶことが重要です。例えば「就職でアピールしたいならTOEIC」「大学留学ならTOEFL/IELTS」「まずは基礎固めに英検〇級」など、目標に応じて使い分けると良いでしょう。試験ごとのメリット・デメリットを理解し、ぜひ今後の英語学習計画に役立ててください。
参考文献・出典:
- English Innovations, TOEFL・TOEIC・英検・IELTSの違いとは?受験すべきテストの結論【比較】. ※IELTSと他試験のスコア換算表を参照。
- English Hub, 5大英語試験を徹底比較 – 最適なテストを選ぶためのガイド. ※TOEICと英検の受験者数、試験形式等に関する記述。
- 4skills, 「違いを比較」英検/TOEIC/GTEC/IELTS/TEAP/TOEFL iBT/ケンブリッジ英検. ※各試験の目的やメリット、利用状況に関する比較データ。
- 4skills, 同上. ※主要試験の実施回数や受験料等に関する一覧。
- アガルート, IELTSのスコア換算表!TOEFL/TOEIC/英検との違いは?. ※IELTSと他試験のCEFR対応・形式比較。
- ENGLISHタイムズ, 英語テスト9種類を比較!目的や試験レベルにあわせて選ぶのがポイント. ※各試験の一覧表および選び方の解説。
- ENGLISHタイムズ, 同上. ※国連英検の概要説明。
- ENGLISHタイムズ, 同上. ※日商ビジネス英語検定の概要説明。
- ENGLISHタイムズ, 同上. ※GCASの概要説明。
- バークレーハウス, Duolingo English Testとは?テストの特徴から対策まで解説. ※Duolingoテストの特徴(受験方式・受験料)。
- バークレーハウス, 同上. ※Duolingoテストの結果通知の速さ・大学での採用状況。