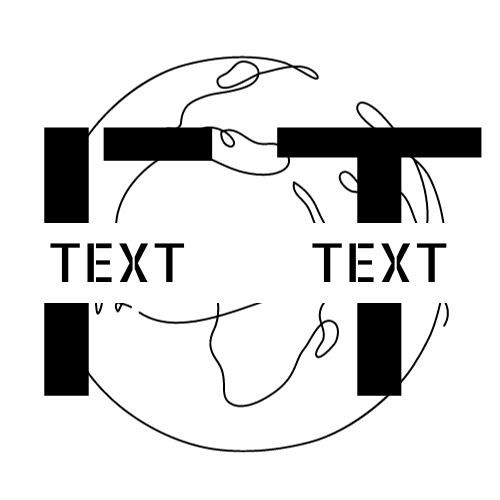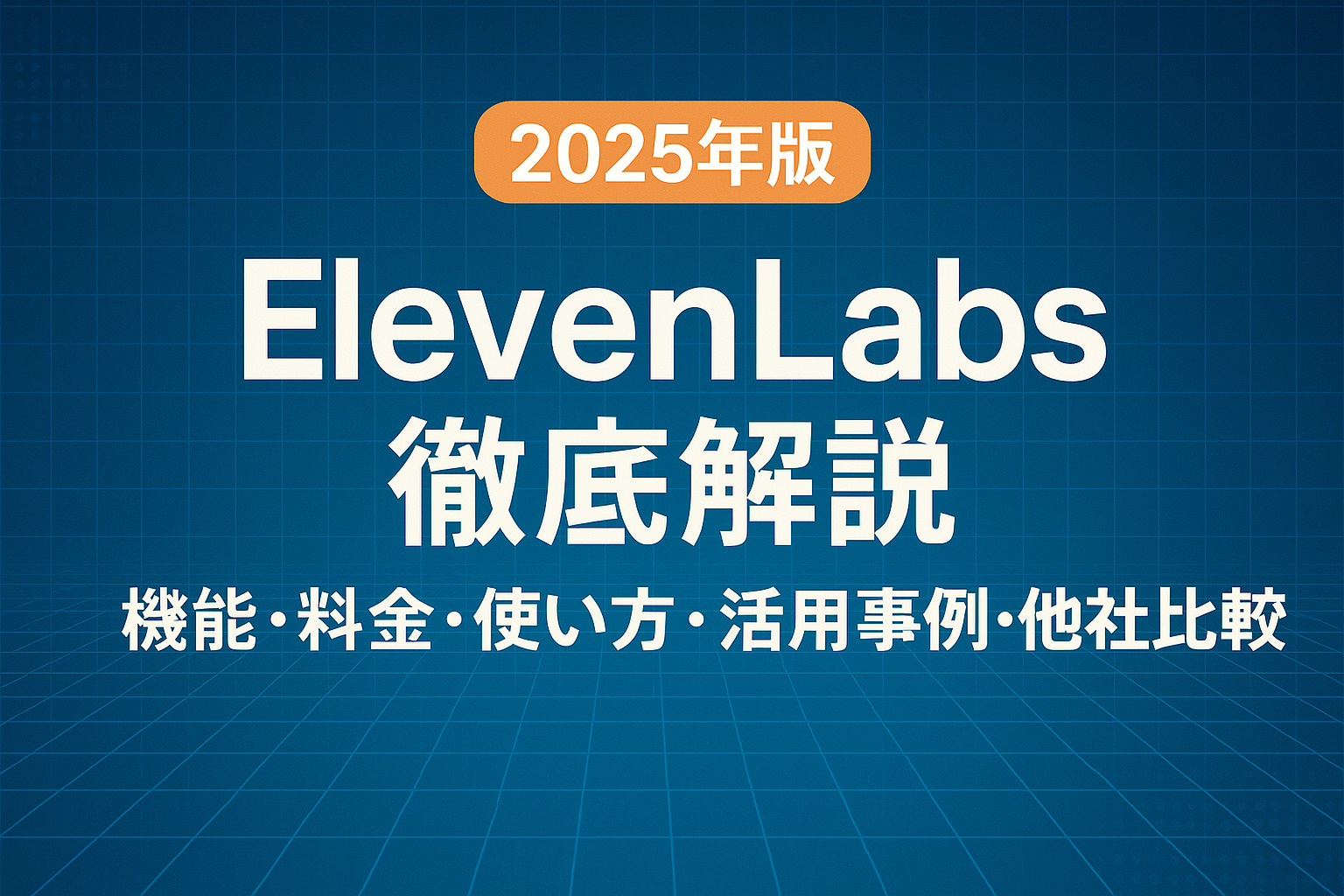主な機能・特徴
ElevenLabsは最新のAI音声合成プラットフォームであり、人間らしい自然な音声生成に特化しています。主な機能として、以下の特徴が挙げられます。
- 高品質なテキスト読み上げ (Text to Speech): テキストを入力すると、抑揚やイントネーションまで自然な音声で読み上げることができます。声のトーンは文脈に応じ自動調整され、質問文では語尾が上がり、文末では下がるなど人間の話し方に近い表現が可能です。音声の感情表現や話速の緩急にも対応しており、AIとは気づかれないほど滑らかな出力が得られます。また生成速度が高速で、長文でも数秒で音声化できるためリアルタイム編集・確認が容易です。
- 多彩な音声モデルと音声種類: ElevenLabsには年齢・性別・話し方の異なる多数の音声モデルが用意されています。英語だけでも113種類以上のプリセット音声があり、落ち着いたナレーション向けの声からキャラクター性の強い声まで用途に応じて選択可能です。さらにユーザーコミュニティによる5,000以上の共有音声が公開されており、ユニークな声も活用できます。公式が用意した高品質なデフォルト音声も長期サポートされ、安定した音声合成に利用できます。
- 音声クローン (Voice Cloning): 自分や特定の人物の声をAIで再現する音声クローン機能を備えています。少量の音声サンプル(数十秒~数分)をアップロードするだけで、その特徴を学習したAI音声を作成可能です 。ElevenLabsではインスタント音声クローン(短いサンプルから即座にクローン生成)とプロフェッショナル音声クローン(長めのサンプルでより高精細に再現)の2種類を提供しており、用途に応じて使い分けられます。※無料プランではクローン機能は使えず、クローン作成には有料プラン契約が必要です。クローン生成時には**本人の声であることの確認(ボイスCAPTCHA)**が実施されるため、他人の声を無断利用するリスクに対策しています。
- マルチリンガル対応: ElevenLabsは日本語を含む70以上の言語での音声合成に対応しており、多言語コンテンツの作成に最適です。各言語ごとに最適化されたモデルにより、言語固有の発音やアクセントも自然に再現します。2025年6月にリリースされた新モデル「Eleven v3」では対応言語が33言語から70以上の言語へ拡張され、日本語や英語はもちろん世界人口の90%をカバーする幅広い言語での読み上げが可能になりました。一つのクローン音声で複数言語を話すこともでき、例えば自分の声で日本語・英語・中国語の各版コンテンツを作るといった応用も可能です。加えて、関西弁のイントネーションに自動変換したり、「サッカー中継風」のような文脈に応じた話し方や効果音混じりの演出も可能になるなど、言語・方言面での表現力が飛躍的に向上しています。
- AI音声エージェントとリアルタイム会話: ElevenLabsは単なる音声合成に留まらず、対話型の音声AIエージェントを構築できるプラットフォームも提供しています。低レイテンシ(モデル遅延75ms)のFlashモデルを使えば、ユーザーとリアルタイムで会話するボイスチャットやコールセンター向けの音声AIを構築可能です 。このAgents Platformでは、電話応対やインタラクティブな音声対話システムを数分でデプロイでき、31言語に対応した双方向会話・応答が実現できます 。音声エージェントはLLM(大規模言語モデル)とも連携でき、ユーザーの質問に対して自然な音声で回答するチャットボットなど、次世代の音声UIを支える技術となっています。
- その他の音声関連機能: ElevenLabsは総合的なオーディオAIプラットフォームとして、多様な機能を搭載しています。
- 音声変換 (Voice Changer): 既存の録音音声を別の声質に変換できます。例えば自分の声を別人格の声に置き換えたり、男性の声を女性声に変えることもワンクリックで可能です 。この機能により、既存コンテンツの声を後から差し替える用途(ボイスオーバーの差替え等)にも対応します。
- AI吹き替え・翻訳 (AI Dubbing): 動画や音声コンテンツを他言語に吹き替える機能があります。元の話者の声色や話し方を保ったまま自動翻訳し、別言語で音声合成することで、ワンクリックで多言語吹替え動画を生成可能です。対応言語は30以上に及び、YouTubeやTikTokの動画URLを入力して自動吹替えすることもできます (※無料・Starterプランでは出力動画にウォーターマークが付きます )。
- ボイスアイソレータ (Voice Isolator): アップロードした音声から人の声だけを抽出し、背景ノイズやBGMを除去する機能です。音質の悪い録音や雑音混じりの音声からクリアな声だけを取り出すことができ、ポッドキャスト編集や録音データのクリーニングに役立ちます。
- 音声効果音生成 (Text to Sound Effects): テキストによる指定で効果音を生成する機能もあります。例えば「群衆の歓声」「雷の音」と入力すれば、その情景に合った効果音をAIが生成します。ゲーム開発や動画編集で効果音素材を迅速に作り出すのに有用です。
- AI音楽生成 (Eleven Music): 音声だけでなく音楽の自動生成にも着手しており、「Eleven Music」というサービスでテキストやプロンプトから任意ジャンルの楽曲を生成する試みも始まっています 。2025年には商用利用可能な音楽生成モデルを発表するなど、音声・音響に関わる総合AIプラットフォーム化を進めています。
- 開発者向けAPI/SDK: ElevenLabsはREST APIとSDKを提供しており、開発者は自分のアプリケーションに音声合成機能を統合できます。公式のPython用・TypeScript用SDKが用意され、数行のコードで高品質な音声を生成可能です。API経由での機能利用としては、テキストを音声データ(WAV/MP3)として取得するTTSエンドポイントや、音声ファイルをテキストに書き起こすSTT(音声認識)エンドポイント、音声変換エンドポイントなどがあります 。APIキーはユーザーアカウントから発行可能で、各音声には固有のVoice IDが割り当てられているため、それらを指定してHTTPリクエストを送ることでクラウド上で音声生成を実行できます 。APIの利用により、例えば自作のアプリやゲーム内でキャラクターボイスをリアルタイム生成したり、ブログ記事を自動音声化するWebサービスを作成したりと、応用範囲が大きく広がります。公式ドキュメントにはAPIの詳細な利用方法やコードサンプルが公開されており、音声合成の自動化やバッチ生成も容易です。
以上のように、ElevenLabsは**「音声」に関するあらゆるAI機能をオールインワンで提供するプラットフォーム**となっており、単なる読み上げソフトに留まらず、クリエイターや開発者、企業の多様なニーズに応えられる柔軟な機能セットを備えています。
料金プランとライセンス
ElevenLabsの料金プランは、個人利用向けの無料枠からプロフェッショナル向けの大規模プランまで複数用意されています。以下に主なプランと特徴をまとめます。
- Freeプラン(無料): 月内最大2万文字程度(約10分相当)の音声生成が可能なお試しプランです。1回のリクエストで生成できるテキストは最大2,500文字までに制限されています。無料プランで作成した音声は非商用利用に限られ、公開時には「ElevenLabsで生成した音声」である旨のクレジット表記(出典表示)が必要です 。また音声クローン機能は無料プランでは利用不可となっています。個人の趣味や評価目的でElevenLabsを試すには十分な枠ですが、商用プロジェクトには利用できない点に注意が必要です。
- Starterプラン($5/月): 月額5ドルで利用できるエントリープランです。月あたり約30分(30,000クレジット)の音声生成が可能で、個人・商用問わず利用できます 。Starter以上の有料プランでは生成した音声を商用コンテンツに自由に利用可能となり、音声へのクレジット表記義務も解除されます 。さらに音声クローンやカスタム音声の作成も可能となり、自分の声をクローンしてナレーションを作成するといった高度な使い方も解禁されます。少額で始められることから、個人クリエイターや小規模プロジェクトでの利用に適しています。
- Creatorプラン($22/月): 月額22ドルの中級プランで、**月あたり約2時間(100,000クレジット)**の音声生成枠があります。Starterプランに比べ約3倍強の文字数を扱えるため、より長尺のナレーションやオーディオブック制作に向いています。加えて、音声クローン機能もより充実しており、複数のカスタム音声を保存・管理したり、プロフェッショナル品質のクローン作成にもアクセスできるようになります(※公式ドキュメント上ではクローン作成はCreator以上が必要とされています )。ElevenLabsを積極的に活用するYouTuberやゲーム開発者など、ヘビーユースに対応するプランです。
- Proプラン($99/月): 月額99ドルの上級プランです。月あたり約10時間(500,000クレジット)もの音声生成が可能で、大規模なコンテンツ制作に耐えうる容量を備えます 。プロプランでは生成高速化やAPIの優先利用などビジネス利用を支えるメリットもあるとされています。企業での動画広告量産や、教育コンテンツの大量生成など、本格的な商用利用にはこのプラン以上が推奨されます。価格は上がりますが、それでも1文字あたりの単価は安価であり、大量の音声を生成するほどコストメリットが出る設計です。
- Scaleプラン($330/月): 月額330ドルの大規模プランで、月あたり約40時間(2,000,000クレジット)に及ぶ音声生成が可能です 。大企業やメディア企業が多言語で膨大な音声コンテンツを生産する場合に適しています。加えてElevenLabsでは、この上にもBusinessプラン($1320/月、約180時間・1100万クレジット/月 )やEnterpriseプラン(エンタープライズ向けカスタム契約)も用意されており、必要に応じて文字数枠の拡大や専用サポートを受けることができます。Businessプランでは最大2,200万文字相当の生成も可能とされており、放送局レベルの大量生成にも耐えるスケーラビリティです。
各プランの主な違いは「月間の文字変換上限」と「商用利用範囲」、そして「利用できる機能」です。無料プランは個人利用限定で商用利用不可、クレジット表記が必要、クローン機能不可といった制限があります。一方、有料プランは全て商用利用可能で、生成音声の取り扱いも自由になります。また音声クローンや高度な機能は有料のみで提供され、特に高精度なプロクローン作成や大量生成には上位プランが必要です。ElevenLabsの場合、月額料金が安価な代わりに文字数上限が明確に区切られているため、自身の利用ボリュームに応じてプランを選択すると良いでしょう。なお、従量課金制ではなく定額制であるため、上限内であれば追加費用を気にせず使える点もメリットです。
ElevenLabsの使い方・操作チュートリアル
ElevenLabsの基本的な使い方について、Webブラウザ版を例に紹介します。利用開始から音声生成までの大まかな手順は以下のとおりです。
アカウント作成とログイン
- 公式サイトでのサインアップ: ElevenLabs公式サイト(elevenlabs.io)にアクセスし、「無料で始める (Get started free)」ボタンからアカウント登録を行います 。登録方法はメールアドレス+パスワードの設定もしくはGoogleアカウント連携が選べます 。登録後、確認メール内のリンクをクリックしてメール認証を完了させるとアカウントが有効化されます 。
- 初回ログイン時の設定: ログインすると、利用目的などに関する簡単なアンケート画面が表示されます(スキップ可能) 。質問に答えて進むと、自動的にElevenLabsの**ダッシュボード(管理画面)**が開きます 。ここには各種機能へのメニューが左側に表示され、右側に使用状況(残りクレジットなど)が表示されます。
- プラン確認と無料枠の利用: ダッシュボード上部には現在のプラン(FreeやStarter等)が表示され、無料プランの場合は残り文字数(クレジット)が確認できます。必要に応じてプランをアップグレードすることも可能です。まずは無料枠内で操作に慣れてみると良いでしょう。
※なお、スマートフォンアプリ(iOS/Android)から利用開始することもできます。公式アプリをインストールし、新規登録すれば同様にホーム画面から音声生成を試せます(アプリ版は現状テキスト読み上げ機能のみ利用可能です)。
テキスト読み上げ(Text to Speech)の手順
ElevenLabsでもっとも基本的なテキスト→音声変換の操作手順を示します。
- メニューの選択: ダッシュボード左のメニューから「Text to Speech」をクリックします 。テキスト入力画面が表示され、中央にテキストボックス、左下に音声設定の項目があります。
- 音声モデルの選択: 「Voice Settings」または画面左下のプルダウンから、読み上げに使用する音声を選択します 。初期状態では英語音声の「Adam」「Antoni」などが選べますが、日本語で読み上げたい場合は日本語対応の音声(例:「Ishibashi」など)を選ぶとより自然です 。また自分で作成したクローン音声がある場合は、ここに自分の声も表示され選択できます 。
- 読み上げ設定の調整: 必要に応じて音声の細かなパラメータを設定します。画面内の「Settings」では声の安定性(Stability)や話し方の多様性(Clarity/Similarity boost)を0.0~1.0の範囲で調整可能です 。値を高くすると安定した落ち着いた読み上げに、低くすると感情豊かで抑揚の付いた読み上げになります。最新のv3モデル使用時は安定性のみ調整可能で、それ以外はAIが自動で最適化します 。初めはデフォルト値(中間値)で問題ありません。
- テキスト入力: テキストボックスに読み上げさせたい文章を入力します 。日本語もそのまま入力可能です(複数言語混在もOK)。無料プランでは一度に入力できる文字数は2,500文字までです 。
- 音声の生成: 入力ができたら「Generate」または「Generate speech」ボタンをクリックします 。クラウド上で音声合成が実行され、数秒待つと下部に生成された音声の再生プレイヤーが表示されます。処理が完了するスピードは非常に速く、体感的には短文ならほぼ即時に、長文でも数秒~十数秒程度です 。
- 結果の確認と保存: 再生ボタンをクリックして、生成された音声を試聴します 。違和感がないか確認し、必要に応じてテキストや設定を修正して再度Generateします。問題なければ、ダウンロードボタンから**音声ファイル(MP3形式)**を保存できます 。ダウンロードした音声は商用利用も可能(※有料プランの場合)なので、動画編集ソフトに取り込む等して活用できます。
📝補足: 生成後の画面で「Share」ボタンを押すと、字幕付きのMP4動画として音声をエクスポートすることも可能です。これは音声に自動生成の字幕を重ねた短いビデオクリップで、SNS共有などに便利な機能です(無料/Starterプラン出力にはウォーターマークが入ります)。
その他主要機能の使い方
ElevenLabsはText to Speech以外にも多彩な機能があるため、主要なものの操作概要を紹介します。
- Voice Changer(ボイスチェンジャー): 手持ちの音声ファイルを別の声に差し替える機能です。左メニューから「Voice Changer」を選び、変換したい元音声をアップロード(またはその場で録音)します。次に、リストから変換先の声(任意のプリセット音声や自分のクローン音声)を選択し、必要ならピッチや話速など音声特性を調整します。設定後「Generate」をクリックすると、アップロード音声の中の話者の声が指定した別声に入れ替わった新しい音声が生成されます。プレビューで確認し問題なければダウンロードできます。これにより例えば英語動画のナレーターの声を日本語話者の声質に変える、自分の声で録音したセリフを別人キャラの声に変換するなどの用途が可能です。
- Instant Voice Clone(インスタント音声クローン): 自分の声をAIにクローンさせる手順です。まず左メニューの「Voice Lab > Instant Voice Clone」を開きます。そこにクローンしたい元音声(自分の声の録音等)をアップロードし、「Next」をクリックします 。続いてクローン音声に付ける名前や話者情報(言語や性別、アクセント等)を入力し、「Save voice」で保存します 。これで数十秒~1分程度待つと自分の声のAIクローンが生成されます。生成完了後は、通常のText to Speech機能で声の一覧に自分のクローン音声が追加されているので、以降は好きな文章を自分の声で読み上げ可能になります。※クローン作成はStarter以上のプラン契約が必要です。プロフェッショナルクローンの場合はより長時間の音声素材を別メニューから提供し、高精度なモデルを作成する手順になります(即時ではなく少し時間がかかります)。
- Dubbing(AI吹き替え): ElevenLabsで動画や音声を翻訳・吹替えする手順です。左メニューから「Dubbing」を選び、「Create new dub」で新規プロジェクトを開始します。まず一次翻訳として、元の音声/動画データと言語を指定して自動翻訳音声を生成します。入力は音声ファイルの他、YouTubeやTikTokのURLにも対応しており、オンライン動画を直接処理できます。翻訳設定を終え「吹き替えを作成」を実行すると、指定言語への吹替え音声や吹替え動画が生成されます。出来上がった吹替え結果を試聴し、必要に応じてダウンロードします。さらに追加で、別の言語への翻訳を行う二次翻訳も可能で、例えば「日本語→英語」で吹き替えた後に、その英語音声を元に「英語→中国語」へ再翻訳吹替えするといった多段階翻訳もワークフロー内で完結できます 。ElevenLabsのDubbing機能により、元の話者の声色や喋り方を保ったまま言語だけを入れ替えられるため、動画コンテンツの多言語展開が劇的に効率化します。
- Voice Isolator(ボイスアイソレータ): ノイズ除去・音声抽出の機能です。左メニューの「Voice Isolator」を開き、雑音を消したい音声ファイルをアップロードします (またはその場で録音も可能 )。アップロード後、「Isolate voice」をクリックすると処理開始し、音声から人の声だけを分離してくれます。完了後、プレビュー再生でノイズが消えたクリアな音声を確認し、良ければダウンロードします。例えば講演録音から話者の声だけ抽出して字幕起こしに回したり、環境音の入った動画からセリフ音声を取り出す、といった用途に使えます。
以上が主要な使い方の概要です。ElevenLabsはインターフェースが直感的で、各機能に沿って指示に従えばプログラミングの知識がなくても高度な音声操作が可能です。公式ヘルプセンターには機能ごとの詳細なガイドも公開されているため、困ったときは参照すると良いでしょう。
活用事例・ユースケース
ElevenLabsはその柔軟な音声生成能力により、さまざまな分野で活用されています。以下に代表的なユースケースと具体例を挙げます。
- コンテンツのナレーション制作: YouTube動画や企業のプロモーションビデオ等のナレーション音声にElevenLabsが活用されています。例えば、自分で話す代わりにAI音声で動画に解説を入れたり、テキスト記事を音声ナレーション付きの動画にするケースです。著名なYouTuberでは、旅行系クリエイターのDrew Binsky氏がElevenLabsの吹替え機能を使い、自身の動画コンテンツを多言語展開しています 。またニュース解説動画を制作する際に、原稿テキストをそのまま高品質なナレーション音声に変換する使い方も一般化しつつあります。
- 翻訳・多言語コンテンツローカライズ: ElevenLabsのAI吹替え(Dubbing)により、動画や音声コンテンツの多言語化が容易になりました。例えば日本語の教材動画を英語や中国語に吹き替えて海外向けに配信するといったことがワンストップで可能です。実例として、日本の大手放送局TBSはElevenLabsと協業し、自社のテレビ番組「KASSO」を複数言語で国際配信する試みにElevenLabsの音声合成を活用しています。韓国のMBC放送系列でもAI音声を使ったコンテンツ制作を進めており、ElevenLabsのTTSやSFXを使ったAI映像作品「Mateo」が国際AI映画祭でグランプリを受賞するなど、その表現力が評価されています。このようにエンターテインメント分野での字幕・吹替え作業の効率化や、グローバル展開における言語の壁の解消に大きく貢献しています。
- オーディオブック・朗読: 長文テキストを読み上げる用途にもElevenLabsが使われています。小説やコラム記事をAI音声で朗読し、オーディオブック化する事例です。ElevenLabsは抑揚やキャラクター表現が豊かであるため、物語の感情を損なわずに音声化できる点が利点です。例えばニュースサイトの記事をAIナレーターに読ませてポッドキャスト配信したり、社内資料を音声教材化して社員の学習効率を上げるなど、文章コンテンツを音声メディアに転用する用途が増えています。ElevenLabsのユーザーにはTIME誌やThe Washington Postといった出版社も含まれており、記事の音声版提供などに役立てられているようです。
- ゲーム開発・アプリ開発: ゲーム内のキャラクターボイスやアプリの音声フィードバックにもAI音声合成が活用されています。ゲームデザイナーはElevenLabsを使って、多様なキャラクターの声を安価かつ迅速に用意できます。特にインディーゲームなどでは声優を多数起用する余裕がないため、ElevenLabsでNPCのセリフを生成するケースが出ています。米国のゲーム会社Paradox InteractiveはElevenLabsの技術を一部タイトルで検証しており、その他Inworld(AIキャラクター対話プラットフォーム)などもElevenLabsの音声を組み込んでいます。日本でも、ゲームMOD制作者がElevenLabsで有志日本語ローカライズの音声を生成するなど、ゲーム音声の民主化が進みつつあります。また、スマホアプリの読み上げ機能(例:ニュースアプリで記事を読み上げ、チャットアプリでメッセージを音声読み上げ等)にもAPI連携で組み込まれ始めています。
- 教育・学習コンテンツ: eラーニングや語学学習向けの教育コンテンツでもAI音声が活用されています。例えばオンライン講座動画の講師音声をElevenLabsで合成したり、児童向け読み聞かせ音声を生成するケースです。チェス学習サイトのChess.comでは、仮想のチェス教師キャラクターにElevenLabsの声を与え、音声で指導できるようにしています。また語学学習では、ネイティブ発音のお手本音声をElevenLabsで作成し教材に取り入れることで、多言語の発音練習を充実させる試みもあります。こうした教育×音声AIの分野は、時間や人材リソースの節約とコンテンツ品質向上の両面で効果が認められています。
- アクセシビリティ支援: 視覚障害者向けの情報読み上げや、高齢者向けの対話アシスタント等、アクセシビリティの領域でもElevenLabsは活用可能です。ニュースや書籍の読み上げサービスに高品質な音声を提供することで、従来の機械的な読み上げより聞き取りやすい情報提供ができます。また聴覚障害者向けには音声→テキスト変換(Speech to Text)機能で字幕生成支援も考えられます。ElevenLabsは社会貢献プログラム「Impact Program」を設けており、教育・福祉団体に技術提供する動きもあります。日本市場においても、超高齢社会の介護・対話支援への音声AI適用が期待されており、ElevenLabs日本法人もそうした分野での展開を視野に入れているようです。
- その他のユースケース: 上記以外にも、ブログや記事の音声化(WordPress記事を自動で音声ポッドキャスト化 )、Discordボットでの読み上げ(チャットメッセージをElevenLabsの声で読み上げる実装 )、コールセンター自動応答(顧客からの電話問い合わせにAI音声で回答 )などアイデア次第で様々な活用がなされています。特に生成系AIブームの中で、「テキストから手軽にプロ品質の声が得られる」ElevenLabsは、多くのクリエイターにとって新しい表現手段・生産性向上ツールとして受け入れられています。2025年現在、ElevenLabsは世界中で数百万人の開発者・クリエイターが利用しているとされ、その用途は今も広がり続けています。
他の音声合成サービスとの比較
AI音声合成の分野ではElevenLabs以外にも多数のサービスが存在します。ここでは代表的なサービス(Play.ht、Descript Overdub、Amazon Polly、Google Cloud Text-to-Speech、CoeFont、VOICEROIDなど)とElevenLabsを機能や品質の観点で比較します。
競合サービスとの比較一覧
各サービスの特徴を簡潔にまとめ、対応言語(日本語対応状況)や音声クローンの有無、価格帯など主要な違いを比較します。
| サービス名 | 主な特徴・機能 | 日本語対応 | 音声クローン機能 | 料金プランの例 (※2025年時点) |
|---|---|---|---|---|
| ElevenLabs | 極めてリアルで表現豊かなAI音声合成。大量の声種(英語プリセット113種以上)と多言語対応(70+言語)。感情コントロールやAI翻訳・吹替え、ノイズ除去、音声クローン等オールインワンの機能セット。API提供あり。 | ◎(対応、質とも非常に高い)– 日本語含め自然な発音とイントネーションを実現。日本市場向けに調整も進行中。 | ◎(対応)– 短い録音から自分の声をクローン可能。プロ品質のクローンも作成可。 | 無料プラン(月2万文字)あり。有料は Starter $5、Creator $22、Pro $99 など。大規模利用向けにScale/Businessプランも。 |
| Play.ht | クラウド型テキスト読み上げサービス。800以上の高品質な合成音声と140言語超に対応し幅広い声質を提供。ポッドキャスト制作に強みがあり、音声生成からホスティング・配信まで統合可能。ユーザーが自分の声をアップロードしてAIボイスを作成するクローン機能も提供。 | ○(対応)– 日本語を含む多言語対応。音質も良好だが、日本語特化ではない。 | ○(対応)–独自のクローン機能あり。他者ボイス提供も存在。 | 月額$19程度からのプラン(※無料試用版あり)。文字数に応じ従量課金制。ElevenLabsより料金は高めとの指摘も。 |
| Descript (Overdub) | 動画・音声編集ソフトDescript内のAI音声機能「Overdub」。ユーザーの肉声からAI音声を生成し、録音無しで後からナレーション文章を挿入可能。編集ツールとしてテキストを編集すると音声が差し替わる画期的なワークフローを実現。コラボ制作や文字起こしとも統合。 | △(一部対応)– 英語向けが中心。日本語も扱えるが声種は限られる。 | ◎(対応)–自身の声をクローンして合成可能(Overdub機能)。著名声の利用は要許可。 | ソフト利用料は月$12~(個人用プラン)。商用利用は高プラン要。Overdub音声の生成文字数に上限あり。 |
| Amazon Polly | Amazon Web ServicesのクラウドTTS。ニュートラル音声とニューラル音声を各言語で提供し、安定した品質。プログラムから使いやすく、AWSサービスとの統合利点大。感情スタイル(ニュース読み・対話風など)のある音声も一部提供。 | ○(対応)– 日本語の合成音声あり(女性声×1・男性声×1等)。イントネーションは標準的だが抑揚は限定的。 | ×(非対応)– 音声クローン機能は無し(AWS内別サービスでカスタム音声構築は可能だが一般向けではない)。 | 従量課金制:$4 per 1M文字前後(標準音声)、ニューラル音声は$16/1M文字程度。初年度500万文字無料枠あり。 |
| Google Cloud Text-to-Speech | Google提供のTTS。WaveNet技術による人間らしい音声を多数用意。言語数は80以上、日本語も高品質。音高や話速のパラメータ調整APIもあり細かな制御可能。 | ○(対応)– 日本語の高品質音声あり(WaveNet声優風など複数)。 | ×(非対応)– クローン機能なし(企業向けにカスタム音声作成サービスあり)。 | 従量課金制:例えばWaveNet音声は$16/100万文字。標準音声は$4/100万文字。無料枠月間合成0.5時間分あり。 |
| CoeFont(コエフォント) | 日本発のAI音声合成サービス。数多くの日本語話者のAI音声をクラウド提供し、ナレーターや声優のような個性的な声が選べる。ユーザー自身の声でAI合成ボイスを作るサービス(CoeFont CLOUD)も展開。日本語での使いやすさやUIに定評。 | ◎(特化)–日本語専用の声が豊富。方言やキャラクター調の音声もあり、日本語用途では選択肢が多い。 | ○(対応)–声のアップロードでクローン作成可能。精度は素材次第だが、手軽に試せる。 | 無料登録で月数百文字~数千文字利用可。商用利用や大量合成は有料ポイント購入制(例:100万文字で数千円程度)。 |
| VOICEROID | AHS社のPC用音声合成ソフトシリーズ。民間の声優やキャラクターの肉声を元に作られた音声ライブラリを使用し、高品質かつクセのある声を出力できる。オフラインでリアルタイム読み上げが可能で、動画制作や実況などに古くから利用者が多い。 | ◎(特化)–日本語のみ対応。関西弁キャラなどもあり。イントネーションは各キャラ収録時に調整済みで自然。 | ×(非対応)– 提供されている既存キャラ音声のみ使用可。他の声をクローン生成する機能はない。 | 買い切り型:音声ライブラリごとにパッケージ販売(1ボイスあたり1万~2万円程度)。商用利用には追加ライセンス契約の場合あり。 |
※上記は一般的な傾向の比較です。音声の自然さ・クオリティ面では総じてElevenLabsが非常に高評価であり、「現状ElevenLabsのリアルさに匹敵するものはない」との声もあります。Play.htも品質向上が著しいものの細部の自然さでElevenLabsに及ばないとの利用者意見があり、逆にPlay.htは対応言語や音声数の豊富さで優位という比較もあります。Descriptは編集ワークフロー統合が強みですが音声ラインナップ自体は限定的です。CoeFontやVOICEROIDは日本語特化ゆえに漢字の読み間違いが少ない、癖のある声が使える等の利点がありますが、汎用的な自由度や表現力では最新のディープラーニング技術を用いたElevenLabsに軍配が上がるでしょう。選択にあたっては用途や予算に応じて、例えば「日本語メインならCoeFont、プロ品質重視ならElevenLabs」といった観点で検討するのが有用です。
日本語対応状況と品質評価・制限
ElevenLabsの日本語対応は、サービス開始当初は限定的でしたが、現在では非常に高いレベルで日本語を扱えるようになっています。2023年頃は主に英語音声が中心でしたが、多言語モデルの改良により日本語の自然な読み上げが可能となり、2025年6月の新モデル「Eleven v3 (alpha)」で本格的な日本語対応が実現しました。
ElevenLabsのCTOも「日本語のような繊細な言語にも我々の技術は非常に適している」と述べており、実際ElevenLabs Japan(日本法人)設立に際しても「日本語は高低アクセントや文脈による微妙なニュアンスが意味を左右するため、自然な抑揚と感情を表現できる音声合成技術は極めて価値が高い」と強調されています。投資家からも「ElevenLabsのプラットフォームは感情豊かでリアルな出力を行い、日本語に特によく適している」との評価を受けています。
品質評価について、テックメディアのGIGAZINEが行ったEleven v3日本語音声のレビューでは、「かなり滑らかに読めており、イントネーションにも無理がなく非常に自然。わずかな緩急も付いていて、知らなければAIによる読み上げとはわからないレベル」と絶賛されています。特に無料ユーザーでも選べる「石橋(Ishibashi)」という日本語特化ボイスでは、「一般男性が淡々と読み上げているような自然さで、抑揚やテンポにもほとんど違和感がない」と評価されました。ElevenLabsによれば、v3モデルでは文章から感情を細やかに読み取り喜怒哀楽を豊かに表現でき、例えば「関西弁で」と指示すれば自動で関西イントネーションに変換することも可能とのことです。さらに「○○風に」といった入力で背景の歓声まで含めた臨場感ある読み上げまで実現できるとされ、表現力の面でも日本語話者の耳を満足させるレベルに到達しつつあります。
一方で制限や課題もいくつか指摘されています。まず、2024年頃までの旧モデルでは日本語の発音にやや不安定さがあり、一部カタカナ語の読みや助詞の抑揚にぎこちなさが見られるケースがありました。しかし日本語対応が本格化したv3ではそうした問題は大幅に改善されています。ユーザーレビューからは「漢字の読み間違いや不自然なポーズが時折発生する」との声もありますが、これも文章を区切る箇所に調整を入れる(読点やポーズ指示タグを挿入する)ことで対処可能です。ElevenLabsは音声タグ機能で「[laugh](笑い声)」や「[sigh](ため息)」などをテキスト中に埋め込むこともサポート予定で、将来的には文章内に「VOICE:関西弁」のようなタグを入れることで方言変換する、といったきめ細かな指定もできる見込みです。
また、日本語対応の音声ライブラリの数という面では、英語に比べると現時点では選択肢が少ない傾向にあります。デフォルトで用意されている日本語音声は限られており(上記「石橋」など数種類)、他は英語話者の声を日本語テキストに流用する形です。しかしElevenLabsは日本市場への本格展開を発表しており、今後は日本語話者の声優・ナレーターの音声を増強したり、日本語UIやサポート体制の充実が図られるでしょう。既に東京に拠点を置くElevenLabs G.K.(合同会社)を設立し、日本企業(NTTドコモやTBS等)との協業も進めています。このことから、日本語へのローカライズ対応や追加ボイス提供は今後さらに強化されると期待されます。
総じて, ElevenLabsの日本語音声は「AIによる日本語読み上げ」としては現状トップクラスの自然さ・表現力を備えており、商用利用にも十分耐えうる品質と言えます。特に感情の込め方や声色のバリエーションでは、従来の日本語TTS(VoiceroidやAITalk等)では難しかったレベルに達しています。今後はユーザーコミュニティからのフィードバックを受けて固有名詞の発音辞書を拡充するなど、細部のブラッシュアップが進めば、更に完璧に近づくでしょう。日本語コンテンツ制作においても、ElevenLabsは強力なツールとなりつつあります。
ユーザーの評価・フィードバック
ElevenLabsは急成長中のサービスということもあり、SNSやコミュニティ上で多くのユーザーレビューや議論が交わされています。全体的な評判としては、**「音声のリアルさが群を抜いている」**という点でほぼ満場一致の高評価を得ています。実際、「ElevenLabsの出力音声品質にネガティブなコメントを見かけることはほとんどない」という声もあるほどで、その自然さは業界トップクラスとみなされています。
**長所(Pros)**としてユーザーからよく挙がる点は:
- 音声品質: とにかく人間そっくりの音声で、アクセントや抑揚も自然。特に英語はもちろん、日本語や多言語でも滑らかに話す点が驚きと評価されています。
- 言語・アクセントの豊富さ: 対応言語や話者の多様性があり、様々な国籍・雰囲気の声を出せる。また外国語訛りの英語やユニークなキャラ声などもコミュニティライブラリで手に入るため、用途に応じて声を探す楽しみもあります。
- ユーザーフレンドリーさ: Web上で完結して使いやすく、インターフェースが直感的であること。また生成スピードが速く待ち時間が少ないので作業効率が良いとの声があります。
- 革新的な機能: 音声クローンやAI翻訳といった新しい機能にも早くから取り組んでいる点が評価されています。声優の権利を守るための仕組み(後述のVoice Library報酬など)も「倫理的なソリューション」として歓迎されています。
一方、**短所(Cons)**や課題として指摘されることがあるのは:
- 発音・テキスト解釈の不安定さ: 一部の声では特殊な記号や文章構造で意図しない読み方になることがある、との報告があります。例えば略語や数値の読み上げ、ポーズの入れ方が不自然になるケースです(※この点は他のTTSと共通の課題ですが、ElevenLabsも完全ではないようです)。ユーザーは生成結果を**校正(proofing)**し、必要に応じて文章表記を工夫して対応しています。
- 特定音声モデルでのグリッチ: 稀に一部の合成音声に機械音的なノイズや破綻(グリッチ)が発生するという報告もあります。特に高い感情表現をさせた場合などで声質が崩れることがあるようですが、バージョンアップで改善傾向です。
- 過剰なセキュリティ検知: 利用者の中には「アカウントで不審なアクティビティと判断されログインが一時ブロックされた」といった声もあります。複数IPからのアクセスなどに対するセキュリティが厳しめという指摘ですが、これもユーザー保護のための措置であり、サポートに問い合わせれば解決するケースです。
- 価格/制限面: 無料プランの制限(2万文字まで・商用不可)がやや厳しいとの声や、商用で大容量使おうとするとPro以上の契約が必要になる点をコスト高と感じるユーザーもいます。しかし「品質を考えれば月$5は安い」「文字数単価では他社より割安」との意見も多く、価格評価は概ね好意的です。
また2023年初頭には、ElevenLabsが悪用(著名人のクローン音声で差別的発言を作成するなど)された事例も報告され議論となりました。これに対してElevenLabs側は早急に音声クローン機能の利用に本人確認を導入したり、利用規約で禁止用途を明確化するなど対策を講じています。多くのユーザーはこれを支持しており、「クローン作成にはセキュリティのためひと手間あるが安心できる」という反応です。またAI音声検出器の研究開発も行われており、生成音声に見えないマーカーを埋め込む技術なども模索されています。
全体として、ユーザーのフィードバックはElevenLabsに対して圧倒的にポジティブであり、「これまで試したTTSの中で最高品質」「創作活動の可能性が広がった」といった声が多数です。一部にある課題も、コミュニティの声を受けて改善が続けられており、リリースから短期間での機能追加・改良ペースにも高い評価が与えられています。
今後の開発ロードマップ
ElevenLabsは2022年の創業以来急成長を遂げており、将来に向けて明確なビジョンと積極的な開発計画を打ち出しています。
2025年1月にはシリーズCラウンドで1億8000万ドルの資金調達を行い、企業評価額は33億ドルに達しました。この資金をもとに、今後数年間で以下のような重点分野の開発が進められる予定です。
- 音声AI研究の深化: ElevenLabsは「AI音声の知能を解明する」という長期目標を掲げており、引き続きより表現力豊かでコントロール性の高い音声モデルの研究開発に注力します。具体的には、感情や話者スタイルをユーザーが細かく調整できる次世代モデル、長文読み上げ時の文脈理解力向上、声のリアルタイム変換精度向上などが考えられます。CTOのPiotr氏率いる研究チームがブレークスルーを起こすべく取り組んでおり、最新モデルEleven v3もその成果の一つです。
- 開発者ツールとAPIの拡充: 音声APIプラットフォームとして、より開発者フレンドリーなSDKや管理機能を強化する方針です。大規模アプリへの組み込みや音声エージェント開発を支援するため、ドキュメントの充実やサンプルコードの提供、エンタープライズ向けの管理コンソール強化などが計画されています。また2025年8月にはElevenLabsの全機能がAPI経由で利用可能となり(v3モデルのAPI公開など)、「AI音声のあらゆる機能をAPIで操作できる総合プラットフォーム」への進化が進んでいます。
- リアルタイム対話・エージェント分野: 会話型AIの分野にも注力しています。今後はリアルタイムストリーミング音声の提供や、インタラクティブな対話エージェント機能の高度化が予定されています。具体的にはコールセンター向けの双方向音声や、自動音声応答システムでの高度なターンテイク(会話の間の取り方)実現、バックエンドで任意のLLMを組み合わせた柔軟な対話シナリオ構築などが考えられます 。実際、投資家からも「音声がデジタルインタラクションの標準になる未来」が期待されており、ElevenLabsはその基盤技術を提供すべく準備を進めています。
- モバイル領域とマルチモーダル展開: スマートフォンやIoTデバイスでの音声AI利用を促進するため、モバイル向けSDKや軽量モデルの開発にも取り組んでいます。既に提供中のモバイルアプリ「ElevenReader」はテキストコンテンツを音声で読み上げるツールですが、今後はさらに対話型のAI音声アシスタントなど、消費者向け音声AIプロダクトにも注力する見通しです。また音声と他のモーダル(映像、文字)を組み合わせたマルチモーダルAIの可能性にも言及しており、音声×映像生成や音声×文字の融合による新しい表現手法の研究も進められているようです。
- グローバル展開と地域適応: Asia太平洋、南米、欧州などでの地域ハブを設立し、各市場に最適化した展開を計画しています。特に日本を皮切りにアジア進出を本格化しており、日本語・韓国語など各言語の特性に合わせた微調整やカスタムボイス提供を進めるとのことです 。また各国の企業やクリエイターと協業し、現地ニーズに沿った音声ソリューションを開発することもロードマップに含まれています。
- AI安全性・倫理の強化: 資金調達発表でも「AI音声の安全性強化」が明言されており 、フェイク音声や悪用への対策技術の開発、ならびに業界標準作りにコミットするとしています。ElevenLabsは2024年に米国で提出されたAI音声関連法案(選挙における合成音声の悪用防止法など)も支持しており、今後は技術的対策と法制度面の両面から「AI音声の健全な発展」に寄与していく姿勢です。
このように、ElevenLabsは**「世界で最も包括的なオーディオAIプラットフォームを構築する」というミッションを掲げ、今後も積極的な研究開発とサービス展開が続く見通しです。IPO(株式公開)も視野に入れていると報じられており、今後5年でさらなる飛躍を遂げることが期待されています。ユーザーにとっては、新機能追加やモデルアップデートのペースが早く、今後も次々と音声AIの新機能や改善**が享受できるでしょう。
セキュリティとプライバシーへの取り組み
AI音声技術は強力な反面、デマ音声の拡散やなりすましといった悪用リスクも指摘されています。ElevenLabsはこうしたリスクに対し、サービス設計や運用ポリシーの面で様々なセキュリティ・プライバシー対策を講じています。
- クローン音声作成の本人確認: 前述の通り、音声クローン機能では**「自分自身の声しかクローンできない」仕組みを導入しています。具体的には、ユーザーがクローン用にアップロードした声が本人のものかを確認するVoice-captcha**が組み込まれており、他人の声を無断でクローンしようとしても弾かれるようになっています。これにより、勝手に有名人の声を複製して偽音声を作る、といった行為を抑止します。またクローン音声の公開にも制限があり、Professionalクローンのみ声の共有が許可されますがそれも本人の裁量であり(声優自身が自分のAIボイスを公開して収益化するなどのケース)、Instantクローンなど他の人が勝手に使えない仕様です。
- 著作権・利用規約の整備: ElevenLabsの利用規約では、ユーザーが生成した音声コンテンツの権利はユーザーに帰属するとしつつ、違法・有害な目的での利用は禁止しています。ヘイトスピーチや誹謗中傷への利用、虚偽情報の拡散に音声を使うことを禁じており、AIが生成した音声であっても社会倫理に反する用途には厳格に対処する姿勢です。万一不適切な利用が発覚した場合、アカウント停止等の措置も取り得る旨が示されています。また商用利用に関しても、無料プランでは不可、有料プランでは可と明確に区分し、誤用がないよう注意喚起しています。
- プライバシー保護: ElevenLabsはヨーロッパ発の企業ということもあり、**GDPR(EU一般データ保護規則)やCCPA(カリフォルニア消費者プライバシー法)**に準拠したプライバシーポリシーを整えています。ユーザーがアップロードした音声やテキストデータはサービス提供目的以外に利用せず、適切に管理・削除できるようになっています。また企業向けにはSOC 2準拠のセキュリティ体制でデータを扱っており、機密情報を含む音声処理についても一定の信頼性を確保しています。自分の声をクローン生成する場合も、その音声データはユーザーのダッシュボード内で管理でき、不要になれば削除可能です。
- Voice Libraryと収益化の仕組み: ElevenLabsはVoice Libraryというプラットフォームを通じて、ユーザーが自分の声を他者に使わせて収益を得る仕組みを提供しています 。既に$2百万以上の報酬が声提供者に支払われた実績があり 、声の権利者に正当な利益を還元するモデルを追求しています。これは声優やナレーターの職業を守りつつAI音声を普及させる取り組みであり、「AIが人間の仕事を奪う」のではなく新たな収益源を生む可能性として注目されています。倫理面では、許可なく著名人の声をアップロードする行為は禁止しており、逆に本人が希望すれば自分のAIボイスを公開してファンに使ってもらえる、といったポジティブな活用を推進しています。
- 安全性に関する研究・提言: ElevenLabsは業界リーダーとして、音声ディープフェイク対策やAI音声の社会受容に関する議論にも参画しています。具体的には、先述のようにアメリカのAI規制法案への支持表明や、欧州におけるAI Actへの意見発信など、健全なルール作りに協力しています。また技術的には、生成音声に識別用の透かし(ウォーターマーク)を入れる技術や、AI音声か否かを検知するアルゴリズム開発などにも投資しているとみられます。公式に「AI Safety」の項目を設け、利用者にも安全な使い方のガイドラインを提示しています。
総じて、ElevenLabsは利便性と安全性のバランスを重視してサービスを運営しています。強力な機能を提供する一方で、「テクノロジーの悪用を防ぎつつ健全に発展させる」という責任を認識しており、それがユーザーコミュニティや声優業界からの信頼にもつながっています。今後も技術の進化とともにセキュリティ・プライバシー対策をアップデートし、ユーザーが安心して利用できる音声AIプラットフォームを目指していると言えるでしょう。
以上、ElevenLabsの機能、料金体系、利用方法から活用事例、競合比較、日本語対応状況、そしてユーザー評価や今後の展望、セキュリティ面まで包括的に解説しました。リアルな音声合成という長年の技術課題に対し、ElevenLabsは突出したソリューションを提供しており、クリエイティブ分野からビジネス現場まで幅広くインパクトを与えています。無料プランで手軽に試せる利点もありますので、興味を持たれた方はぜひ実際に触れてみて、その性能を体感してみることをお勧めします。今後もアップデート情報や事例が続々出てくると思われますので、ElevenLabsの公式ブログやコミュニティにも注目していきましょう。
参考文献・情報源: 本レポートではElevenLabs公式サイトおよびドキュメント 、国内外メディア記事 、ユーザーコミュニティのレビュー など一次情報を中心に参照しています。